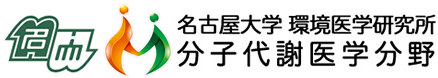教授挨拶

分子代謝医学分野は、令和7年7月で教室開設10周年を迎えました。本研究所では、教授交代とともに体制が一新されますので、文字通りゼロからのスタートでした。これまで、研究所内、大学内、名古屋地域、そして関連学会関係の皆様に多大なご支援を賜りながら、教室メンバーとともに、私が思い描いていた研究室の姿を少しずつ形にすることができています。定年までの折り返し地点を迎え、これまでの歩みと今後の展望について改めて考えてみたいと思います。
■研究内容と今後の目標: これまで一貫して、栄養・代謝と炎症・免疫の接点である“イムノメタボリズム(免疫代謝)”に注目して、生活習慣病や自己免疫疾患の病態解明と新規治療戦略の開発に取り組んできました。“細胞死”と“細胞内代謝”という切り口でメカニズム研究を進めるとともに、“医工連携”の視点を導入して社会実装を目指し、いくつかの重要な研究成果も出てきました。新しい展開として、神経系によるイムノメタボリズム制御という個体全体を俯瞰した概念や、空間トランスクリプトーム解析や超微細構造解析、ハイスループット生細胞解析などの最先端技術にも挑戦しています。今後も、基礎と臨床をつなぐ独自の研究スタイルを模索していきたいと考えています。
■次世代育成と教室文化: 既に10名程の大学院生が博士号を取得し、関連学会でYIAを受賞するなど対外的にも高く評価されています。卒業生の活躍も目覚ましく、日本学術振興会特別研究員(PD/RPD)4名、創発的研究支援事業採択3名、さらに2名がアカデミアで教授や准教授に就任しました。特に印象的だったのは、OB・OGが現教室メンバーに研究の楽しさや学びの重要性を伝えてくれたことです。所属や専門が異なったとしても、それぞれの立ち位置で元気に頑張っている姿を見ることで、こちらも励みになりました。教室開設当初より、多彩なバックグラウンドを持つヘテロな集団を目指し、学内外の様々な研究者と活発に交流できる“壁のない”研究室を目指してきましたが、この理念が着実に根付いてきたことを嬉しく思います。
■今後のビジョン: 昨年から研究所執行部の一員として、組織運営にも携わることになりました。自分自身が研究に割くことのできる時間も限られてきましたが、この新たな責任を教室の更なる発展の機会と捉えています。最近、研究が複雑化・高度化して、1人の研究者や1つの教室ではカバーできないことが増えてきました。教室の枠を超えた研究チームの編成や研究環境の改善など、執行部の立場だからこそ実現できることに取り組みたいと思います。幸運なことに、様々な特長を有するメンバーに恵まれ、共同研究者とは高いテンションを共有する関係を構築することが出来ました。ドアの向こう側にはどのような景色が広がっているのか、ワクワクする感覚を忘れずに、臨床応用に繋がる“夢”のある基礎医学研究に取り組む所存です。
引き続き、皆様のご支援の程を宜しくお願い申し上げます。
2025年10月
菅波孝祥
名古屋大学環境医学研究所 分子代謝医学分野のホームページを訪れていただき、有難うございます。平成27年7月に着任し、早いもので5年が経過しました。お世話になった先生方には、心より御礼を申し上げます。立ち上げ当初に参加して下さった大学院生全員が無事に論文発表し、次のステップに進んだことで、一区切りを実感しています。私は着任時に45歳、定年退職まで20年でしたので、教室運営を5年間 x 4回と捉えることにしました。幸いにも、最初の5年間で教室の基盤はほぼ整いました。新しい研究成果が出始め、YIA受賞などでメンバーの活動が認められると、さらに若いメンバーの励みになっています。一方で、次の5年間に臨むにあたり、心新たに教室の進むべき方向性を考える必要があります。以下に、研究の内容や目標に関して、思うところを記載してみます。
■研究内容: 教室開設時に、キーワードとして“慢性炎症”と“栄養”を掲げました。我々の研究の出発点は、「過栄養で生じる脂肪組織の慢性炎症」です。メタボリックシンドロームにおいて、脂肪組織炎症がアディポカインや遊離脂肪酸を介して全身臓器に拡大・波及するように、我々の研究対象も、脂肪組織から肝臓、腎臓、中枢神経系などに拡がってきました。我々は、特にマクロファージなどの免疫担当細胞に着目して、この複雑な病態メカニズムを解き明かそうとしています。一方で、免疫担当細胞自身の細胞内代謝やエネルギー供給が、分化や機能を制御することが明らかになり、新しい学問領域として“Immunometabolism(免疫代謝)”が世界的な潮流になっています。我々は、医学系研究科の連携講座「免疫代謝学」として、代謝と免疫の表裏一体の関係を明らかにしたいと考えています。
■研究目標: 私自身は、臨床(内科学講座)と基礎(研究所)の両方で活動してきましたので、将来的に、研究成果を臨床へ還元することが最大の目標です。しかしながら、創薬や検査への応用を真剣に考えると、医学系研究者のみで出来ることには限界があります。そこで我々は、目標実現の手段として“医工連携”に注力してきました。例えば最初の5年間で、フェニルボロン酸を主要な成分とするグルコース応答性の高分子ゲルを基盤技術として、血糖変動に応答して自律的にインスリンを放出する人工膵臓様デバイスの開発に取り組み、小動物において良好な治療効果を得ました。今後、本デバイスの社会実装を進めるとともに、様々な生活習慣病を克服する医工連携を推進したいと考えています。
このような研究を推進するために、研究室の内外で多彩なバックグラウンドを有する研究者と交流し、(なるべく)限界を作らず、自由な発想で取り組みたいと心がけています。幸運なことに、様々な特長を有するメンバーに恵まれ、共同研究者とは高いテンションを共有する関係を構築することが出来ました。ドアの向こう側にはどのような景色が広がっているのか、ワクワクする感覚を忘れずに、臨床応用に繋がる“夢”のある基礎医学研究に取り組む所存です。
引き続き、皆様のご支援の程を宜しくお願い申し上げます。
2020年9月
菅波孝祥
分子代謝医学分野は、平成27年7月1日に名古屋大学環境医学研究所(ストレス受容・応答研究部門)に発足した新しい研究室です。基礎研究と臨床研究を繋ぐ立ち位置で、生活習慣病の病態解明や新しい治療法の開発に貢献したいと考えています。
ライフスタイルの欧米化に伴って、我が国においても肥満が増加し、メタボリックシンドロームや様々な生活習慣病の誘因となっています。生活習慣病は遺伝素因と環境因子の相互作用により発症する代表的な多因子疾患ですが、我々を取り巻く環境の変化と生体のストレス応答が大きく関わっています。このメカニズムを明らかにするためには、1つの分子や1つの細胞に注目するだけでなく、各臓器を構成する多彩な細胞の相互作用や神経系、内分泌代謝系、免疫系を介する複雑な臓器間ネットワークを理解する必要があります。このような、細胞内、細胞間、臓器間の各階層におけるメカニズムが複雑に絡み合って形成される生活習慣病を解くキーワードとして、私たちは“慢性炎症”に注目しています。また、様々な環境変化の中で、私たちは、特に“栄養”に興味を持っています。即ち、過栄養や栄養飢餓といった栄養の“量”の変化に加えて、動物性の飽和脂肪酸や魚油に多く含まれるω-3多価不飽和脂肪酸、アミノ酸などの栄養の“質”の変化が、どのようにして“慢性炎症”に繋がるのかを明らかにしたいと考えています。
私はこれまでに、京都大学と東京医科歯科大学において、臨床(内科学講座)と基礎(研究所)の両方で活動してきました。医学部の他に、農学部、薬学部、理学部、工学部など多彩なバックグラウンドを有するメンバーと研究に取り組んできたことが、私の財産になっています。分子代謝医学分野では、メンバーが各々の特長を活かして、自由闊達に切磋琢磨する研究環境を醸成することにより、環境変化に対する適応反応とその破綻がもたらす“慢性炎症”を解き明かしたいと思います。研究生活では、思い通りにならないことが多く、一進一退の状態が続きます。学生や若手研究者の方には、このような過酷な環境の中でも、“喜び”を見つけて粘り強く、地道に努力を続けて欲しいと思います。最初の頃は、日々の実験を上手く行った“喜び”でしょう。しばらくすると、学会発表や論文を通して研究内容を他の研究者に伝える“喜び”を感じるはずです。そして、研究内容が周りから評価される“喜び”を知ってしまうと、あなたは研究の虜になることでしょう。
名古屋の地で、新しい仲間とともに、臨床応用に繋がる“夢”のある基礎医学研究に取り組む所存です。皆様のご支援の程を宜しくお願い申し上げます。
2015年7月
菅波孝祥